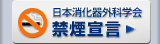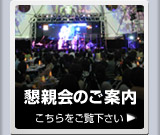プログラム
| <<プログラム一覧に戻る |
10.ワークショップ
| 1) |
消化器術後不定愁訴への対応:理論と対応 消化器手術後の不定愁訴としての腹部を中心とした消化器症状あるいは神経精神症状をともなう症例は少なくない.嘔気・嘔吐・倦怠惑・腹部膨満・腸管過敏・便秘・創部痛・睡眠障害など多くの症状がある.これら複数か重なって多種多様な不定愁訴を訴えてくる場合には,対症療法的に経過をみることも少なくない.それらのなかには消化管機能障害や吻合部運動障害・狭窄・潰瘍という場合もありうる.そこで,不 定愁訴の原因を追求ていただき,局所消化管機能や脳相と消化管機能との関係についての理論を探り,それに基づいた治療や対応を紹介いただきたい. |
| 2) |
02-1 膵頭十二指腸切除術の再建法、吻合法の提案と課題 02-2 膵頭十二指腸切除術の再建法、吻合法の提案と課題 膵頭十二指腸切除術においては,消化管再建,胆道再建,捧管再建が必須となるが,その手順や配列順などについてのgold standardはない.縫合不全の頻度,再建部の開存性,残存組織・臓器機能の維持,が臨床的に重要項目である.本ワークショップでは,術後のdelayed gastric emptying,膵・胆道再建部位の縫合不全,術後胆管炎の発生頻度や残膵機能の維持といった観点から,再建法,吻合法にけるについて紹介していただくとともに、これらの課題について今後の解決の見通しについて討論していただきたい. |
| 3) |
再発腫瘍の外科治療法および集学的治療方針 −肝・胆・膵− 肝・胆・膵悪性疾患における再発腫瘍において,外科的切除を期待できる症例は必ずしも多いとはいえず,外科治療を実施するには原則として非治癒因子を生じないと判断できる症例に限定される.肝細胞癌の多くは背景疾患として慢性肝炎ないし肝硬変を有することから,再発肝癌の治療方針は腫瘍因子とともに肝予備能を考慮する必要があり,結果として,複数回の根治的手術か行われる症例は限られる.一方で,RFAやTACEなど肝胞癌に対する治療法のオプションは多数有り,根治的切除ができなくとも手術を含めた各種の治療法を組み合わせることにより,局所の制御が可能な症例も多い.一方,胆道癌・膵痛では根治切除後であっても再発率は高く,通常は局所発に対する再切除や,両葉に多発する肝転移に対して切除適応とされる症例は少ない.近年.胆道癌・膵癌ではgemcitabineやs-1を軸とした化学療法の有効性か示されつつあり,再発腫瘍に対しても化学療法と手術を軸とした集的治療により延命効果を得られる可能性がある.ここでは,再発肝・胆道・膵癌治療のstrategyについて,とくに各施設での経験をふまえた集学的治療方針,などにつき論議いただきたい. |
| 4) |
再発腫瘍の外科治療法および集学的治療方針 −大腸・肛門− 大腸癌では,肝・肺転移,局所再発の頻度が高く,これらの再発腫瘍に対する適切な治療が予後改善には重要である.肝・肺転移については,外科的切除を中心とした治療によって良好な成績が報告されているが,新規抗がん剤の導入によりその治療法への概念も変化しつつある.果たしてそれは正しいことなのであろうか.局所再発については,明らかに延命効果を期待できることとして,病巣数の少ない局所再発に対しては根治的切除を行ことである.しかし,多臓器合併切除などの拡大手術をともなう場合には,根治性と患者QOLへの影響を考慮する必要がある.ー方,肛門腫瘍は,その組織型によって治療方針は大きく異なってくる.本ワークショップでは,外科手術と学療法,放射線療法の集学的治療成績も含めて,大腸・肛門腫瘍再発の治療方針を討議していただきたい. |
| 5) |
肝門部胆管癌の治療戦略:切除断端と剥離面の陰性化を目的とした術式の工夫と限界点 肝門部胆管癌の外科治療では,胆管剥離面と肝(胆)管切離断端の癌陰性化か治癒切除を成し遂げる上で重要である.大量肝切除,場合によっては膵頭十二指腸切除,脈管合併切除の付加により治癒切除か可能となりうるが,時にover surgeryとなっていることもある.また,肝機能や全身状態の不良な症例では,その過大な侵襲から術式選択に難渋することがある.本ワークショップでは,摘除剥離面および切除断端陰性化を図た肝切除,脈管合併切除と再建,膵頭十二指腸切除の併施とともに,可能な限りの局所切除による手術の低侵襲化を目指した術式の工夫,などを紹介いただき,その実際の成績を示していただきたい. |
| 6) |
炎症性腸疾患に対する外科治療の現状 炎症性腸疾患の治療法については,血球成分除去療法,免疫抑制剤,抗TNFα抗体を用いた薬物療法など新しい内科的治療の効果を認めている.しかし,治療抵抗性の潰瘍性大腸炎や外科手術を余儀なくされるクローン病などの症例も存在する.これらの手術適応と手術時期については,内科医との十分な連携をとりつつ慎重に決定されることが望ましい.炎症性腸疾患に対する新しい内科的治療の現状を考慮した手術適応,適切な手術時期病態別の術式の在り方とその具体的操作を紹介していただきたい. |
| 7) |
術前放射線療法、高用量化学療法施行例に対する消化器癌手術:私はこうしている 高度進行癌に適応となる術前放射線療法,高用量化学療法後に実施する外科治療において周術期合併症発生が高頻度あるいは重症化し易いとのことが常に問題となる.しかし,投与法の工夫や周術期管理の発展によりそれらの安全性は向上しているとも言われている.また,対象臓器によっては術前補助療法によりCRを得ることも経験するなど,良好な長期予後を獲得できうることもありえるが,その頻度は極めて低いことも事実である.すわち,それらの有効性については確立したものではない.予後を何よりも左右しているのは手術成績としてのQuality dControlで,操作性の困難さや易出血性,組織の脆弱性に焦点が当てられよう.そこで,手技上の工・注意点や周術期管理方針などについて論じていただきたい. |
| 8) |
再発腫瘍の外科治療法および集学的治療方針 −食道・胃− 再発腫瘍に対し外科的切除を期待できる症例は必ずしも多いとはいえず,外科治療を実施するには原則として非治癒因子を生じないと判断できる場合に限定される.他に外科治療法に依存することとしては,切除を断念しQOL改善に対して行われるバイパス手術かあげられる.一方,新規抗癌剤によって生存期間の延長に寄与するということで新展開がみられるようにいわれてはいるが,それらのMSTは未だ満足する結果が得られていないも現状である.どのような症例に外科治療を行うべきか,集学的治療を担う適切な補助療法を外科治療の前後のいずれで実施するのか,などの問題点に対して的確な治療方針を打ち出していただきたい. |
| 9) |
消化器外科領域のtranslational researchの抱える問題点とその将来展望 トランスレーショナルリサーチとは基礎研究で得られた成果を臨床治療に応用するためにエビデンスを作る学問である.しかしながら,試験デザインによっては臨床研究が進みにくく,立案数に比して完終半の低いことが問題となっている.これまで本邦において行なわれた消化器外科領域でのトランスレーショナルリサーチの経験とその成果を提示していただきたい.医師主導型と企業主導型の臨床研究に焦点を当て,今後の日本におけるトンスレーショナルリサーチ遂行上の課題を明確にしていただき,明日の臨床研究への礎を築きあげるための機会としていただきたい. |
| <<プログラム一覧に戻る |