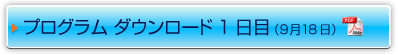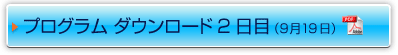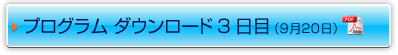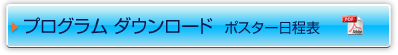学術プログラム
変更は随時更新いたします。
坂本レクチャー
| 「Translating Clinical Trial Results to Clinical Practice」 | |
| 座長: | 永井 良三(東京大学大学院医学系研究科) |
| 演者: | Anthony N.DeMaria(UCSD, USA) |
招聘講演
| 「The Vulnerable or High-Risk Plaque in Acute Coronary Syndrome: A 10-Year Projection of Understanding and Prevention」 | |
| 座長: | 山岸 正和(金沢大学医薬保健研究域 医学系 臓器機能制御学・循環器内科) |
| 演者: | Valentin Fuster (Mt. Sinai School of Medicine, USA) |
| 「Surgical Left Ventricular Reconstruction for Ischemic Cardiomyopathy」 | |
| 座長: | 髙本 眞一(三井記念病院) |
| 演者: | Gerald D.Buckberg (David Geffen School of Medicine at UCLA, USA) |
| 「The Use of the NCDR® Clinical Registries to Promote Comparative Effectiveness Research」 | |
| 座長: | 山科 章(東京医科大学 第2内科) |
| 演者: | Jack Lewin(American College of Cardiology, USA) |
| 「Central Aortic Pressures and Cardiovascular Outcomes ? The future of blood pressure measurement?」 | |
| 座長: | 鄭 忠和(鹿児島大学) |
| 演者: | Bryan Williams (University of Leicester, UK) |
| 「Improving Heart Failure Care Using Internet Based Telemedicine」 | |
| 座長: | 松﨑 益德(山口大学大学院医学系研究科 器官制御医科学講座 器官病態内科学) |
| 演者: | Alfred A.Bove (Temple University Hospital, USA) |
| 「動脈硬化の分子イメージング」 | |
| 座長: | 吉川 純一(大阪掖済会病院) |
| 演者: | Aikawa Masanori(Brigham and Women’s Hospital、Harvard Medical School, USA) |
| 「New Insight and Therapeutic Strategy for Diastolic Heart Failure」 | |
| 座長: | 下川 宏明(東北大学大学院医学系研究科 循環器病態学分野) |
| 演者: | Karl Swedberg (Sahlgrenska Academy, Gothenburg University, Sweden) |
| 「The Impact of the Major Prophylactic Implantable Cardioverter」 | |
| 座長: | 小川 聡(国際医療福祉大学三田病院) |
| 演者: | David S.Cannom (Good Samaritan Hospita, USA) |
| 「Who Gets the Heart Attack, and How Concerned Should You Be?」 | |
| 座長: | 玉木 長良(北海道大学大学院医学研究科 病態情報学講座 核医学分野) |
| 演者: | Jagat Narula (UCI, USA) |
会長講演
| 「メタボリックシンドローム、高血圧と循環器疾患-基礎・疫学から臨床まで-」 | |
| 座長: | 飯村 攻(札幌医科大学 名誉教授) |
| 演者: | 島本 和明(札幌医科大学 内科学第二講座) |
栄誉賞記念講演
| 冠動脈インターベンションと歩んだ四半世紀 | |
| 座長: | 松﨑 益德(山口大学) |
| 演者: | 山口 徹(虎の門病院) |
特別記念講演
| 「自然科学としての心臓病学」 | |
| 座長: | 島本 和明(札幌医科大学) |
| 演者: | 坂本 二哉(半蔵門病院) |
特別企画
| 「医療者への提言」 ~75歳、エベレスト登頂への挑戦・アンチエイジングと不整脈の克服~ |
|
| 座長: | 北畠 顕(北海道大学 名誉教授 医療法人枚岡病院 名誉院長) |
| 演者: | 三浦 雄一郎 (プロスキーヤー 株式会社ミウラ・ドルフィンズ) |
| 「医療事故に関する第三者機関の動向」 | |
| 座長: | 矢崎 義雄(独立行政法人 国立病院機構 理事長) |
| 演者: | 山口 徹(国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 院長) |
| 「再生医療」 | |
| 座長: | 堀 正二(地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター) |
| 「心筋再生治療の現状と展望」(Regenerative Therapy for Failing Heart) 演者:澤 芳樹(大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座 心臓血管外科学) |
|
| 「心臓病への再生医療」 演者: 松原 弘明(京都府立医科大学) |
|
市民公開講座
※上記タイトルをクリックすると詳細がご覧いただけます。
| 1.「高齢者が心得るべき循環器疾患の常識と対応」 | |||||||||||||||||
| 座長: | 島本 和明(札幌医科大学 内科学第二講座) | ||||||||||||||||
| 演者: | 日野原 重明(聖路加国際大学) | ||||||||||||||||
| 2.心臓突然死に関する市民公開講座 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 3.ストップ・ザ・メタボ~心臓病を防ぐために~ | |||||||||||||||||
| ご挨拶: | 島本 和明(札幌医科大学 内科学第二講座) | ||||||||||||||||
| 講演: | 「特定健診・保健指導スタート1年、現状と課題について」 木村 博承(厚生労働省健康局生活習慣病対策室長) |
||||||||||||||||
| 講演: | 「メタボ肥満から心臓病へ ~臨床の立場から」 斎藤 重幸(札幌医科大学内科学第二内科講師) |
||||||||||||||||
| 講演: | 「いまからでも遅くないメタボ予防・健診」 野口 緑(尼崎市国保年金課保健師) |
||||||||||||||||
| 講演: | 「食は医なり ~内臓脂肪の減らし方」 伊藤 和枝 (天使大学栄養学科教授) |
||||||||||||||||
| 講演: | 「運動習慣が決めて」 宮地 元彦(国立健康・栄養研究所プロジェクトリーダー) |
||||||||||||||||
アジアンセッション
| States of Arts: Asian Arrhythmia Practice | |
| 座長: | 平岡昌和(東京医科歯科大学・厚生労働省労働保険審査会)/ Teo Wee-Siong (National Health Centre, Singapore) |
| 「Total Management of Atrial Fibrillation」 | |
| Koichiro Kumagai(International University of Health and Walfare,Heart Rhythm Center,Fukuoka Sanno Hospital) | |
| 「Catheter Ablation ob Atrial Fibrillation」 | |
| Lo Li-Wei(Divisyon of Cardiology,Taipei Vaterans General Hospital,Taiwan) | |
| 「Catheter ablation of ventricular tachycardia - Experience in our center - 」 | |
| Harumizu Sakurada(Hiroo Hospital,Tokyo,Japan) | |
| 「Catheter Ablation for Ventricular Tachycardia - Asian Perspective」 | |
| Teo Wee-siong (National Health Centre,Singapore) | |
シンポジウム
※タイトルをクリックすると座長の言葉がご覧いただけます。
-
最近の心エコーの進歩(指定) 座長: 吉田 清 (川崎医科大学 循環器内科)
増山 理 (兵庫医科大学 循環器内科) -
最近の心エコーの進歩はめざましい。近年開発された3次元エコー、ストレイン、組織追跡(2Dトラッキング)などさまざまな手法がさらに進化し、現在では日常の検査にも用いられつつある。3次元エコー法はこれまでの画像構築が必要なものからリアルタイムへと移行し、ビジュアル的にも大きく改善されてきた。今後3次元エコーを用いた新たな指標が定着することも視野に入ってきたと言っても過言はない。一方、ストレイン、組織追跡などの新手法の開発により、心機能の評価対象が心臓全体から心筋局所に移ってきた。さらに最近では、心筋局所の機能が方向(longitudinal, circumferential vs radial directions)によって異なることが分かり、今後心筋虚血や疾患の早期発見などへの臨床応用が大いに期待される。また、多くの循環器疾患においては安静時には無症状で、労作時にのみ症状がみられることが多い。心筋酸素消費量を増やす手法としての運動負荷も重要であるが、運動による反応性の違いを心エコー検査で見ることによることも最近では行われつつある。このシンポジウムでは単に最近の新しい心エコー技術を紹介するだけではなく、心エコーの新技術・新手法を駆使することにより分かってきた新しい知見の有用性・限界、さらには今後の方向性についても言及したい。
-
今、心臓血管外科手術のスタンダードを考える(指定) 座長: 松居 喜郎 (北海道大学病院 循環器外科)
坂田 隆造 (京都大学大学院 医学研究科 器官外科学講座 心臓血管外科学) -
心臓血管外科手術は、テクノロジーの進歩と相俟って急速に変貌をとげつつある。僧帽弁閉鎖不全手術における弁置換術から形成術へのシフト、感染性心内膜炎での弁形成術の試み、On-pomp CABGからOff-pump CABGへ、大動脈基部病変でのBentall型手術から自己弁温存基部置換術への試み、大動脈瘤に対するステントグラフト治療等、従来のスタンダード術式からのパラダイムシフトをめざして数多くの挑戦が続けられ、一定の成果ももたらした。しかし一方で、新しい術式は概念的により良い結果をもたらす術式であるはずだとの説明で、その時々のスタンダード術式に対する優越性を確保されたかのように取り扱われ、一定の評価が科学的に検証されるまでの数年間、いわば野放しの状態にある。
新しい術式、より低侵襲の術式は今後も追及されるべきであるが、この数年間に登場した新しい術式は萌芽的なものも含めて数多くあり、今、この時代における心臓血管外科手術のスタンダートは何か、そもそも外科手術法におけるスタンダードを満たす要件は何か、を議論し整理しておくことは、今後の心臓血管外科学の発展に正当性を与えるうえで重要なことと考える。演者の真摯な討論を期待したい。
-
高血圧ガイドラインと心臓病診療(指定) 座長: 島田 和幸 (自治医科大学 内科学講座循環器内科学部門)
松岡 博昭 (宇都宮 中央病院) -
心臓病の主要な3病態、すなわち心肥大・心不全、虚血、不整脈に高血圧は深く関与する。心肥大・収縮不全にレニン・アンジオテンシン・アルドステロン(RAA)系が促進因子として働き、RAA系を阻害することによって可逆的に病態を改善できる。一方,心収縮能が保持された拡張不全による心不全に対するRAA系阻害薬の有効性は未だ証明されていない。虚血心に対する降圧薬の有効性も、心筋梗塞後のβ遮断薬、RAA系阻害薬において確立している。さらに長時間作用型Ca拮抗薬も血圧降下に比例したプラークの進展阻止が示された。不整脈では、心房細動の発症予防にアップストリーム療法としてRA系阻害薬が注目されている。このように、心疾患の各種病態に応じた降圧薬治療の有効性が明らかにされつつある。降圧目標に関しても、近年の大規模臨床試験では、正常血圧者をも対象にして、その有効性が明らかにされている。従ってより、厳格な降圧が望ましく、130/80mmHg未満にコントロールすることが望ましい。いわゆるJカーブ現象は拡張期血圧において、なお否定しきれていない。本シンポジウムで心臓病と高血圧の関わりを以上のような観点からアップデートしたい。
-
心臓病診療における今後の展開と医療制度の在り方 (指定) 座長: 山口 徹 (虎の門病院 院長)
和泉 徹 (北里大学医学部 循環器内科学) -
わが国ではかつてないサイズとスピードで少子高齢化が進むであろう。今後の医療問題はこの潮流と密接に連動する。また、心臓病診療は人口の高齢化に寄与してきた。心臓救急やカテーテル診療の進歩は高齢化を産み出す。一方、高齢化社会は心臓病患者を多数輩出する。最終像である慢性心不全然りである。しかもこの疾患は指数関数的に疾病負担を増加させる。多疾患有病者である心不全は心事故を発生させ、それを介して患者負担、家族負担、社会負担を惹起し、結果として大きな医療需要を要求する。貴重な人的・物的医療資源の投入が強制される。日本独自の相互医療保険もこのような展開を想定していなかった。心臓病診療も、長命達成のみを一義的な目標に掲げてきた。しかし、今後の展開とそれに見合う医療制度の整備においては、この基本認識を先ず見直す必要がある。豊かな少子高齢化社会を早急に創生するには、疾病負担を軽減する心臓病診療が求められている。疾病管理や予防医学の役割、それに合理的な医療資源の確保と活用も問われる。そこで、今回のシンポでは、1.少子高齢化と心臓病、2.診療技術の展開、3.医療保険の見直し、4.疾病負担とその軽減、5.疾病管理と予防医学、6.医療資源の分配、などに焦点を当て広く演題を求めたい。多くの方々の活発な応募を希望する。
-
DES時代の冠動脈治療の問題点(公募) 座長: 宮崎 俊一 (近畿大学医学部 循環器内科)
児玉 和久 (大阪警察病院 尼崎中央病院 日本大学医学部 ) -
我が国において2004年にシロリムス溶出性ステント(SES)が保険適用となり5年が経過した。この間の実臨床おいてに、SESの再狭窄抑制効果はこれまで従来型ステントでは再狭窄率が高いとされていた冠動脈病変においても有効であり、顕著な再狭窄率の減少が確実となった。しかしながらMcFaddenらの報告により1年以上の長期間が経過した後でもステント内血栓症が発生し得ることが明らかとなり、SESの新たな問題となっている。一方、冠動脈バイパス術の領域においてもoff pump手術をはじめとする技術進歩により合併症頻度が減少しており、1988年AHAガイドラインで示された重度冠動脈疾患における冠動脈バイパス術の長期予後における優位性はSES導入後の現在でも妥当なものとして広く認識されている。さらにCOURAGE研究ではスタチン系薬物をはじめとする強力な抗動脈硬化治療により冠動脈疾患の長期予後改善効果が期待されることが示されており、薬物治療の進歩も極めて大きい。このように冠動脈疾患治療の3本柱のそれぞれにおいて大きな進歩があるという背景のもとに本シンポジウムでは現在の冠動脈疾患治療に関する問題点とその対応について議論する。特に我が国におけるデータの蓄積が最近になって進んできており、欧米におけるガイドラインとは異なる点について議論を深めたい。
-
急性冠症候群に対するクリニカルパス ― その再評価と今後の展望(公募) 座長: 住吉 徹哉 (財団法人 日本心臓血圧研究振興会付属 榊原記念病院 循環器内科)
小川 久雄 (熊本大学大学院 循環器病態学) -
クリニカルパスとは特定の疾患に罹患した患者のためにまず医療の目標と成果を設定し、その目標を効率よく達成するために必要な行為と時期を示したマップである。これまで多くの施設で種々の疾患に対する独自のクリニカルパスが考案され、標準的な医療を実践するうえで重要な存在になりつつある。クリニカルパスの導入はEBMやガイドラインに準拠した医療を実践することにも繋がり、医療の標準化を図り、医療の質を最小限確保することにもなる。また業務の効率化やチーム医療を推進するための教育的効果なども期待されている。
急性冠症候群はクリニカルパス導入の効果が最も期待される急性疾患の代表であるが、その導入に先進的な施設からは有用性とともに種々の問題点についての分析も報告されている。急性冠症候群の病態は極めて多様であり、それに対する治療の選択肢は多岐にわたる。合併症の少ない軽症例に対してはクリニカルパスの適用は比較的容易でその成果も得られやすいが、合併症の出現や病状の変化などでバリアンスとして除外されたり、退院調整の問題などで予定通りに進まない事例も少なくない。本シンポジウムでは、急性冠症候群に対するクリニカルパスの効用を再評価するとともに、プログラムの作成や実践するうえでの課題を整理して、さらに有意義なものにするための展望についても討論したい。
-
慢性心不全の治療ガイドラインを検証する (公募) 座長: 筒井 裕之 (北海道大学大学院 医学研究科循環病態内科学)
百村 伸一 (自治医科大学付属さいたま医療センター 循環器科) -
数々の大規模臨床試験によって、収縮不全の患者に対するレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系抑制薬やβ遮断薬、さらには心臓再同期療法(CRT-D)の予後改善効果があきらかにされ、エビデンスに基づいた慢性心不全の標準的治療がガイドラインとして推奨されている。このような治療の進歩は患者の予後の改善に寄与してきたと考えられる。しかし一方で、疫学研究では予後の改善は十分ではないことも報告されている。その理由として、ガイドラインの遵守が不十分で、治療効果が得られていないことや大規模臨床試験の患者は、実際の患者とは大きく異なっていることなどが指摘されている。実際、治療薬剤の組み合わせ・投与量、心臓再同期療法の適応、心房細動・腎不全・貧血・睡眠時無呼吸など頻度の高い合併症に対する治療、駆出率が保たれた心不全や治療抵抗性重症心不全に対する治療など、ガイドラインと日常診療のギャップに苦慮する患者が少なくない。
本シンポジウムでは、わが国の慢性心不全患者の実態をふまえて、ガイドラインに基づく治療の有効性と限界・課題をあらためて認識するとともに、今後ガイドラインに取り入れられることが期待される新たな治療の展望を討議することによって、ガイドラインの検証を行いたい。
-
ICDを用いた治療戦略と将来展望 (公募) 座長: 井上 博 (富山大学医学部 第二内科)
奥村 謙 (弘前大学大学院医学研究科 循環呼吸腎臓内科学) -
植え込み型除細動器(ICD)は心室性不整脈による不整脈死を防ぐ確実な治療手段であり、二次予防の意義は確立されたといえる。しかし一次予防としてのICD治療に関しては、議論は分かれているように思われる。例えば海外で行われたMADIT-IIではICDによる一次予防の有効性が示されたが、わが国の患者でMADIT-IIの基準を満たすものの生命予後は、欧米の患者に比べるとそれほど悪くはなく、ICDの必要性は必ずしも高いとはいえない。またわが国で多いとされるBrugada型心電図を示す無症候例に、ICDによる一次予防を施すのか否かについても意見の完全な一致を見ているわけではない。ICD植え込み後には作動を抑制するために大部分の例で抗不整脈薬を併用しているが、その効果の程度や除細動閾値に対する薬剤の影響も問題となる。ICD治療に関して多くの切り口から検討を加え、わが国におけるICDの適切な治療戦略と将来展望を議論できることを願っている。
パネルディスカッション
※タイトルをクリックすると座長の言葉がご覧いただけます。
-
急性心不全の治療戦略 (指定) 座長: 友池 仁暢 (国立循環器病センター 院長)
吉川 勉 (慶應義塾大学医学部 循環器内科) -
急性心不全の病態はあまりにも多種多様であるがゆえに、治療の系統的整理が捗々しくない実情がある。驚くべきことに低心拍出状態とうっ血に対して、それぞれカテコラミン製剤とループ利尿薬が盲目的に使われている場合もある。しかし、近年急性心不全においても眼前の危機にのみ目を奪われ、反射的に対症療法をすることが必ずしも良い結果を招くわけではないことも明らかとなりつつある。年々、治療選択肢も豊かになっており、ホスホジエステラーゼ阻害薬やヒト心房利尿ホルモン製剤、硝酸薬など様々な薬剤が提示されている。欧米では大規模な登録研究が行われ、急性心不全の病態に対する理解が深まりつつある。急性心不全では従来循環動態を中心に診療が行われていたが、最近では神経体液因子、炎症、腎機能、貧血など他臓器との連関を重視した理解が深まりつつある。薬物治療抵抗性心不全の場合は、限外ろ過装置、補助循環装置、人工心臓など非薬物治療も普及しつつある。さらに睡眠呼吸障害に対しては呼吸管理の面から治療の奏効性が報告されている。心不全急性増悪患者の院内予後および退院後長期予後を予測すべく、バイオマーカーを用いた検討も盛んに行われている。本パネル・デイスカッションでは、このように急速に変貌しつつある急性心不全の病態の理解と治療の考え方を中心に議論を深めたい。
-
最新の弁膜症診療と心エコーの役割(指定) 座長: 竹中 克 (東京大学医学部附属病院 検査部)
尾辻 豊 (産業医科大学 第二内科学) -
心臓弁膜症は変貌しています。リウマチ性心臓弁膜症は減少しましたが、大動脈弁狭窄症はすごい勢いで増えています。高齢者・腎透析例で大動脈弁狭窄はよく遭遇し、心雑音を聴取する最も頻度の多い病気という印象を持ちます。逸脱による僧帽弁逆流も症例が多く、機能性・虚血性僧帽弁逆流例はたくさん見ます。機能性三尖弁逆流や連合弁膜症も多く見られます。また、治療も変化してきています。僧帽弁逆流の外科治療が弁置換術から弁形成術へ変わり、大動脈弁膜症に対する自己弁温存手術(大動脈弁形成術)も始まり、良好な成績が報告されています。僧帽弁狭窄に対するPTMCは以前からありましたが、カテーテルを用いた僧帽弁逆流の弁形成や大動脈弁置換術も行われ始めています。二次性僧帽弁逆流に対して心臓再同期療法も広く行われ、その効果の機序・予測が議論の的となっています。また、3次元心エコー法を始め心エコー法自体も発展し変化しています。
このように心臓弁膜症は疾患自体も疾患の治療も変化してきています。弁膜症の診療が変わってきている中、心エコーの弁膜症例に果たすべき役割も変わらざるをえません。心エコー法も変化し、新たな評価法が出現しています。本パネルディスカッションにおいては、このように変貌を遂げつつある心臓弁膜症診療における最新の心エコー評価法をアップデートしたいと思っています。
-
小児期発症心疾患の非薬剤治療の新たな展望(指定) 座長: 佐野 俊二 (岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 心臓血管外科)
中澤 誠 (財団法人 脳神経疾患研究所付属総合南東北病院 小児・生涯心臓疾患研究所 所長) -
小児期発症心疾患は、形態異常とその術後、不整脈、心筋疾患、川崎病などの後天性疾患が治療の対象となる。それらに対する非薬剤治療は、その第一が手術で、その他にカテーテル治療、それらの組み合わせ(ハイブリッド治療)、ペースメーカ治療などが挙げられる。
新たな展望として、手術では、長期予後を見据えた新生児手術、成長を勘案した弁手術など、カテーテル治療では心房中隔欠損閉鎖に続いて、心室中隔欠損、卵円孔などの閉鎖が次の段階であろう。海外の一部では、カテ室とオペ室を隣接させて、カテーテル治療と手術を組み合わせるハイブリッド治療が症例数を増やしているが、我が国でも一部の施設で試みられ、リスクを低減し治療成績の向上に寄与する可能性を示している。ペースメーカ治療の展望は、第一には小児ないし先天性心疾患でのICD植え込みで、その経験が増えつつあるが、未だ、解決すべき多くの問題がある。第二は心機能を念頭に置いたペーシングで、その一つは心室電極そのものによる長い余命期間での心機能への影響の問題、二つ目は小児および先天性心疾患における心不全治療としてのCRTの諸問題である。
これらの治療は、我が国のみならず世界的にも未だ十分の経験がなく、未知の部分が多い。このセッションでは、演者自身の経験と、外国の先進的な治療を比較して、その問題点および我が国における将来への展望を示せれば、と考える。
心臓構築形態修復
血管治療
心不全治療
不整脈治療
CHDのカテ治療:defect closure, Stent for vasc stenosis (branch PS, re-CoA)
心不全へのCRT
不整脈:Ablation、PM植え込み、ICD植え込み
ハイブリッド治療:カテ治療と手術治療
-
動脈硬化ガイドラインと心臓病診療(指定) 座長: 北 徹 (神戸市立医療センター中央市民病院 院長)
山科 章 (東京医科大学 第二内科) -
生活習慣の変化からわが国では動脈硬化に関連する循環器疾患が増加しており、動脈硬化は死因、QOL低下、医療費、労働力損失、いずれの面からみてもわが国における最重要な病態と言って過言でない。動脈硬化の進展は緩徐で、初期は無症状である。しかし、一旦、進展すると不可逆的となり、急激に進行し、しかも突然に発症することが多い。動脈硬化疾患の重症化を阻止するには早期の段階から生活習慣改善や薬物治療などの介入を必要とするが、一部の患者だけでなく、幅広く適切かつ標準的な介入が行われなければ成果はえられない。そのための指針が診療ガイドラインである。診療ガイドラインを定義すると、「医療者と患者が特定の臨床状況で適切な決断を下せるよう支援する目的で、体系的な方法に則って作成された文書」である。わが国においても日本動脈硬化学会から2007年に動脈硬化性疾患予防ガイドラインが発表されている。心臓病診療においても本ガイドラインはきわめて重要な意味を持つが、さらに幅広く活用されるためには、臨床的な裏づけが必要である。本パネルディスカッションでは、心臓病診療の観点から本ガイドラインの意義、有用性、問題点などについて検討したい。
-
冠循環に迫る(指定) 座長: 砂川 賢二 (九州大学大学院 医学研究院 循環器内科)
三浦 哲嗣 (札幌医科大学 内科学第2講座) -
近年、冠動脈疾患の画像診断やそれに基づく経皮的介入手技は飛躍的な進歩を遂げ、虚血性心疾患の治療に劇的な効果を上げている。その一方で、冠循環を巡る基礎的な研究も著しい進歩を遂げている。本来心臓は他の臓器や組織に血流を供給するための臓器である。運動時は心拍出量が著明に増大し、心臓のエネルギー消費も比例して増加する。このエネルギーは心筋の好気的代謝で産生される。しかしながら、この好気的な代謝を支え心筋に酸素を供給している冠動脈血流は、心収縮の直接的な力学効果により収縮期には殆ど途絶し、専ら拡張期にしか流れない。さらに、冠静脈の酸素飽和度は低く、心筋の酸素摂取量を上げるためには、血流の調節が不可欠になる。すなわち、心臓が充分なポンプ機能を発揮するためには、心臓自身の収縮という不利な状況に打ち勝って血流を調節する必要がある。そのため、冠循環には巧妙な調節機構が組み込まれている。本パネルディスカッションでは最新の心筋のエネルギー代謝、心収縮の冠血流に及ぼす影響、冠微小循環制御、さらに冠動脈硬化によるこれらの機能の障害と病態の関連について議論を深めたい。このパネルディスカッションで得られる最新の知見が、冠動脈疾患の新たな診断・治療戦略の開発の一助になることを願っている。
-
心原性心停止の実態と対策:救急蘇生国際ガイドライン2010に向けて(指定) 座長: 野々木 宏 (国立循環器病センター 心臓血管内科)
長尾 建 (駿河台日本大学病院 循環器科 心肺蘇生と救急心血管治療センター) -
院外心停止の実態は、ウツタイン様式を用いた登録により明確になりつつあり、その結果必要な対策が明確になってきた。市民による心肺蘇生法実施率の増加や心停止から除細動までの時間が短くなり、また自動体外式除細動器による社会復帰例の増加が報告されている。しかし、心停止全例の救命率はなお低い。心停止の原因の50%以上を占める心原性は、迅速な通報、迅速な心肺蘇生法の実施、迅速な電気的除細動、迅速な専門的治療の4つの救命の鎖が時間の遅れなく機能すれば、その社会復帰率は改善する。本パネルディスカッションでは、心停止後の心脳蘇生に必要な事柄を実態から蘇生後のケアまで含め検討を行いたい。
-
心不全診療における国内大規模臨床研究の成果(公募) 座長: 長谷部 直幸 (旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野)
小室 一成 (千葉大学大学院医学研究院 循環病態医科学) -
加齢とともに発症頻度が増加する心不全は、超高齢化社会を迎えるわが国において、極めて重要性の高い疾患である。死亡率、発症率、有病率などわが国独自の疫学データは、残念ながら十分とは言えず、病型、治療法と予後の関連など欧米との相違を把握した上で明らかにされるべき問題点は少なくない。わが国では、基礎疾患として虚血性心疾患の割合は低く、死亡率も欧米と比べて低いと推測される。収縮機能が正常に保たれたいわゆる拡張不全の患者は、女性、高齢者に多く、わが国においても30%以上を占めると考えられている。これらわが国の心不全患者の病態を把握し、治療法を確立することは重要な臨床的課題である。現在いくつかのpopulation-based studyや登録研究が進行中であり、中間報告もなされつつある。また、前向き研究によっていくつかの薬物介入の効果も検討されており、これらの最終的な成果に期待が集まっている。本パネルでは、心不全診療におけるわが国の大規模臨床研究のこれまでの成果と今後の展望についてディスカッションしたい。
-
心房細動の治療戦略(公募) 座長: 相澤 義房 (新潟大学大学院 循環器分野)
三田村 秀雄 (東京都済生会中央病院 循環器科) -
心房細動は頻脈性不整脈として患者のQOLを損なうのみならず、血栓形成を促して脳塞栓を引き起こし、ときに生命予後を脅かす。それに対する治療戦略が近年大きく進展しつつある。例えば非薬物治療であるカテーテルアブレーションは心房細動の根治療法として注目されているが、治療成績の向上に伴って適応も拡大されつつある。薬物治療についてはupstream治療としてACE阻害薬やARB、あるいはスタチンなどによる心房細動発生予防の成績が次々と報告されている。問題の多いdownstream治療としての抗不整脈薬についても、J-RHYTHM、J-BAF、フレカイニド用量試験など日本独自の試験が実施され、治療戦略に多大な影響を与えている。発作性心房細動ではリズム治療が勧められるが、ここではいかに安全性の高い薬剤を選択するかが課題となる。一方、持続性心房細動においては一般にレート治療が勧められるが、ベプリジルのような特殊な薬剤によるリズム治療も選択肢に含まれるようになった。抗血栓療法ではワルファリンの適用がより明確にされ、安全かつ効果的な使用法が確立されつつある。さらには心房選択性の抗不整脈薬や抗トロンビン薬、凝固因子Xa阻害剤なども開発中である。本パネルではこれら心房細動の新しい戦略を紹介すると共に、それらをどの症例にどの場面で選択使用すべきかを論じ、心房細動をより安全に管理するための一助としたい。
ビジュアルワークショップ
※タイトルをクリックすると座長の言葉がご覧いただけます。
-
PCIに求められる画像診断(指定) 座長: 一色 高明 (帝京大学医学部付属病院 循環器科)
西村 重敬 (埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科) -
PCIは、急性冠症候群の死亡率減少に有効な治療であり、CABGによる延命効果が証明されている、「心機能低下あるいは高度な狭心症を伴う多枝病変例、LMT病変例」等においても、CABGと同等の治療効果が得られることが明らかにされ、その適応は拡大しつつある。一方、安定した冠動脈疾患に対するPCIの予後改善効果は、1980年代のCABG対内科治療の無作為試験と同じく、内科治療に比して症状の改善は得られるものの、その延命効果はないことが報告されている。
冠動脈疾患の画像診断法には、病変の質的診断の可能な冠動脈CT、MRI、従来からPET、SPECT等の非観血的検査と、観血的検査である血管超音波法、血管内視鏡、OCT等があり、単独あるいは統合的診断法として用いられる。得られる情報の性質から、機能・生理的評価と形態・解剖的評価に分けることもできる。治療ガイドラインでは、安定した冠動脈疾患に対するPCIの根拠に、心筋虚血あるいは心筋viabilityの証明が挙げられている。画像情報を加えたPCIによる治療戦略によって、予後改善効果が得られるかどうかは臨床上の最重要な課題であるが、新しい画像診断法ではその根拠の集積が不十分となる限界がある。そのような現状の中で、本ワークショップでは画像情報が、PCIの適応決定あるいはデバイスの選択や手技的戦略にどのように役立つのかを、成績と予後改善効果との関連および医療資源の有効利用の観点も加えて、議論したい。
-
頻拍性不整脈に対するマッピングシステムの進歩(指定) 座長: 青沼 和隆 (筑波大学 循環器内科)
新田 隆 (日本医科大学 心臓血管外科) -
新たなマッピングシステムの普及によって、従来カテーテルアブレーションの治療成績が低かった心房頻拍や非通常型心房粗動等の難治性頻拍症の治療成績が大幅に向上し、更には従来根治不可能とされてきた基礎心疾患を有する心室頻拍に対する治療も頻繁に行われるようになった。これは頻脈性不整脈の治療において、新たなマッピング装置による電気的興奮の旋回路や起源が可視化されるに至ったことだけではなく、新たなマッピング装置の臨床導入によって基礎心疾患合併心室頻拍や慢性心房細動等における背景に存在する組織学的な不整脈基質の可視化が可能となったことによるところが大きいと考えられる。
この新しいマッピングシステムによる進歩は、単に内科領域におけるカテーテルアブレーションのみではなく、不整脈外科の領域においても達成されている。心房細動に対するメイズ手術は一般にはマッピングを必要としない術式であり心房切開線は同一であったが、新しいマッピングシステムによる術中マッピングで得られた電気生理学的所見に基づいて至適術式を決定するmap-guided心房細動手術等は合理的な方法と言える。更に基礎心疾患合併心室頻拍手術においては、頻拍の起源あるいは緩徐伝導路の局在を明らかにする必要があり、種々のマッピングにより治療の進歩が得られている。
今回、この5年の間に著しく進歩し、目を見張る治療成績の向上が得られた分野である頻拍性不整脈の非薬物治療におけるマッピングの役割とこれからについて、このビジュアルワークショップを通じて多くの先生と共に議論したい。
-
心臓領域におけるMDCTの最先端(指定) 座長: 栗林 幸夫 (慶応義塾大学医学部 放射線科学)
南都 伸介 (関西労災病院 循環器科) -
近年におけるCTの進歩は目覚しく、特に1998年に登場したMDCT(multidetector-row CT)はこの10年の間に著しい進歩を遂げ、心臓・冠動脈の非侵襲的な画像化が可能となった。現在では64列CT装置が普及し、冠動脈のみならず冠静脈、肺静脈、大動脈弁、心房・心室の形態などの評価に広く使われている。特に冠動脈領域では、有意狭窄の有無の評価に関して高い診断精度が報告され、またプラークの存在診断、性状診断についても有用性が報告されている。
冠動脈CTの画質は64列CTによって格段に進歩したが、診断精度をより向上させ従来の冠動脈造影を置き換えるには、まだいくつかの課題が残されている。これらは、空間分解能および時間分解能の向上、内腔の評価を困難にする冠動脈壁の高度石灰化への対応、被曝線量の低減、不整脈への対応などである。これらの問題を解決するために、種々の技術開発や工夫が行われつつあるのが現状である。本ワークショップでは、これらの課題をbreakthroughするようなコンセプトや技術、工夫、その臨床応用の成果に関して、ビジュアルな発表を期待する。
コントロバーシー
※タイトルをクリックすると座長の言葉がご覧いただけます。
-
PCIか外科治療か(指定) 座長: 斉藤 滋 (札幌東徳州会病院 循環器内科)
夜久 均 (京都府立医科大学大学院 医学研究室 心臓血管・呼吸器外科学) -
PCIか外科治療か?については過去20年来多くの比較試験がなされてきた。現在のところRandomized studyにおいてはrepeat revascularizationの点からはCABGが優っているがsurvivalにおいては差が無いというのが大方の傾向であり、一方、膨大な症例数でのObservational studyでは、特に重症3枝病変、LMT病変においてはrepeat revascularization、survivalのどちらにもCABGに軍配が上がるという結果が示されている。今年2009年にAmerican College of Cardiology Foundationから出されたAppropriateness Criteria for Coronary RevascularizationでもLMTと重症3枝病変はCABGがappropriateだとされている。しかしながら、この間の時代の流れの中で、PCIではPOBAからBare Metal StentそしてDrug-Eluting Stent、またCABGにおいても静脈グラフトから内胸動脈、さらに複数の動脈グラフトが使用されるようになり、またOPCABによって手術の低侵襲化が図られるようになった。そしてそのようなtechnologyや技術の進化に文献上の比較試験が時間的に追従できていないこともあり、これらの結果が必ずしもcontemporaryなpracticeを反映しているとは言い難い面もある。そのような背景から、過去のPCI vs CABGの議論ではなかなか議論がかみ合わず平行線を辿ることもよく見受けられた。今回同様なテーマで議論をするにあたって、なんとか内科、外科双方の議論がかみ合い、お互いの治療の持ち味を認識できるようなセッションにしたいと思う。その目的で、内科からは外科治療にふさわしいと思われる症例、あるいはシリーズを、また外科からは外科治療よりもむしろPCIにふさわしいであろうと思われる症例の提示をしていただき、その治療選択において深く議論でき、またお互いの治療を十分に理解する機会にしたい。
-
慢性虚血性心疾患の診断アプローチ:CTかRIかAGか(指定) 座長: 玉木 長良(北海道大学医学研究科 病態情報学講座)
笠貫 宏(早稲田大学 理工学術院) -
慢性虚血性心疾患の診断的アプローチとして負荷心電図の他、多くは負荷心エコーや負荷シンチが利用され、その上で治療を目的とした冠動脈造影(CAG)が実施されるのが欧米の一般的な考え方である。他方本邦では、施設の制限などの関係で診断的CAGが好んで用いられてきた。最近はマルチスライスCTを用いて非侵襲的に冠動脈の描出が可能となり、診断的CAGに置き換わりつつある。昨今は限られた医療資源の中で最も有効な検査手法を選択することが求められており、そのためには診断的アプローチとしてのCT, RI, CAGの各検査法の特徴と、他の検査法に対する優位性を十分理解する必要がある。このセッションでは慢性虚血性心疾患の診断、重症度、および治療戦略などの観点から、各検査法の専門家により、各々の手法がどのように優れるのか、またどのような場合にどう使い分けるべきかについて徹底討論していただく。この討論を通して明日の診療に役立つ検査の指針が示されることを願っている。
-
非弁膜症性心房細動の血栓予防 どこまですべきか(指定) 座長: 堀江 稔 (滋賀医科大学 呼吸循環器内科)
是恒 之宏 (独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター 臨床研究センター長) -
循環器学会心房細動治療ガイドライン2008では、非弁膜性心房細動の血栓予防において抗血小板薬は第一選択薬からはずされ、原則的に抗凝固薬を使用するかしないかの選択をすることになる。リスク評価としてCHADS2スコアが使用されているが、1)コントロール良好な高血圧や糖尿病はCHADS2スコア1点か、2)欧米と同じ75歳以上という年齢のラインでよいか、3)ハイリスクでアブレーション成功例はいつまで抗血栓療法を行うか、4)CHADS2スコア0点症例で2日以上続く心房細動発作の除細動に抗血栓療法は必要か、5)手術や内視鏡の際の抗血栓療法をどうするか、6)抗血小板薬が2剤使用されているステント留置後の冠動脈疾患にハイリスク心房細動を合併する場合、など実臨床では抗血栓療法の使用やPT-INRの目標設定に迷う場面も少なくない。このコントロバシーでは、これらのポイントについて、抗凝固療法積極派と慎重派の立場から討論してみたい。
ビデオライブデモ
| 「外科」 | |
| ここまでできる日本の僧帽弁形成技術 | |
| 「内科」 | |
| 1 | PCIビデオライブ 「PCIにおけるビデオライブの意義(Young operatorのstep upのためのTraining)」 |
| 2 | EVTビデオライブ 「EVTにおけるビデオライブの意義(下肢動脈、腎動脈、頸動脈)」 |
教育講演
| 末梢動脈疾患の外科治療 「インターベンション治療(PPI)のブームの影に潜むもの」 |
|
| 座長: | 野村 雅則 (藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院 循環器内科) |
| 演者: | 笹嶋 唯博 (旭川医科大学 第一外科) |
| 冠攣縮性狭心症 「薬剤治療のスタンダードを再認識する」 |
|
| 座長: | 平山 篤志 (日本大学医学部 内科学系 循環器内科学分野) |
| 演者: | 吉村 道博 (東京慈恵会医科大学 循環器内科) |
| 心臓核医学検査による心不全診断 | |
| 座長: | 野原 隆司 (財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 心臓センター) |
| 演者: | 山崎 純一 (東邦大学医療センター大森病院) |
| 大動脈疾患 「どこまでステント治療をすすめるべきか」 | |
| 座長: | 古森 公浩 (名古屋大学大学院 血管外科) |
| 演者: | 栗本 義彦(札幌医科大学 医学部) |
| 不整脈疾患の外科的治療 | |
| 座長: | 幕内 晴朗 (聖マリアンナ医科大学 心臓血管外科) |
| 演者: | 三崎 拓郎 (富山大学医学部 第一外科学) |
| 川崎病の冠動脈病変その後 | |
| 座長: | 石井 正浩 (北里大学医学部 小児科学) |
| 演者: | 富田 英 (昭和大学横浜市北部病院 循環器センター) |
| 心疾患の周産期管理を再考する | |
| 座長: | 倉林 正彦 (群馬大学大学院医学系研究科 臓器病態内科学) |
| 演者: | 中谷 敏 (大阪大学院医学系研究科) |
| 「IVUSとOCT:冠動脈疾患の診断・治療における有用性と限界」 | |
| 座長: | 代田 浩之 (順天堂大学 循環器内科) |
| 演者: | 赤阪 隆史 (和歌山県立医科大学 循環器内科) |
| 「生活習慣病としての非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)」 | |
| 座長: | 檜垣 實男 (愛媛大学大学院 病態情報内科学) |
| 演者: | 加藤 淳二 (札幌医科大学医学部 内科学第四講座) |
|
「循環器医に知ってほしい消化器疾患 -胸痛を訴える消化器疾患とアスピリン潰瘍-」 |
|
| 座長: | 犀川 哲典 (大分大学医学部 臨床検査診断学講座) |
| 演者: | 篠村 恭久 (札幌医科大学医学部 内科学第一講座) |
| 「抗リン脂質抗体症候群の診断と最近の知見」 | |
| 座長: | 梅村 敏 (横浜市立大学大学院医学研究科) |
| 演者: | 小池 隆夫 (北海道大学大学院医学研究科 内科学講座・第二内科) |
| 「術前機能評価で循環器内科医に求めること」 | |
| 座長: | 木原 康樹 (広島大学大学院 医歯薬学総合研究科 循環器内科学) |
| 演者: | 並木 昭義 (札幌医科大学 名誉教授 市立小樽病院 麻酔科) |
| 「脳血管インターベンションの今後を展望する 頸動脈ステント留置術」 | |
| 座長: | 野出 孝一 (佐賀大学医学部 循環器・腎臓内科) |
| 演者: | 野中 雅 (白石脳神経外科病院 脳血管内治療センター) |
| 「心不全と心臓リハビリテーション」 | |
| 座長: | 後藤 葉一 (国立循環器病センター 心臓血管内科) |
| 演者: | 上嶋 健治 (京都大学大学院医学研究科 EBM研究センター) |
| 「Endovascular Therapy for Peripheral Vascular Disease」 | |
| 座長: | 齋藤 穎 (敬愛病院) |
| 演者: | 横井 良明(岸和田徳洲会病院) |
モーニングセッション
| 薬剤溶出性ステント「抗血小板薬の問題点」 | |
| 座長: | 水野 杏一(日本医科大学 内科学講座 循環器・肝臓・老年・総合病態部門) |
| 演者: | 中川 義久(天理よろづ相談所病院 循環器内科) |
| 急性冠症候群 「血液診断を考える」 | |
| 座長: | 川名 正敏(東京女子医科大学附属青山病院 院長) |
| 講演: | 木村 一雄(横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター 心臓血管センター) |
| 心臓突然死の原因診断 「どこまでどう診断するか」 | |
| 座長: | 新 博次(日本医科大学多摩永山病院 院長) |
| 講演: | 清水 渉(国立循環器病センター 心臓血管内科) |
| 「BNP測定でわかること」 | |
| 座長: | 長谷部 直幸(旭川医科大学 内科学講座循環・呼吸・神経病態 内科学分野) |
| 講演: | 斎藤 能彦(奈良県立医科大学 第一内科学) |
| 肺高血圧 「評価と治療を教わる」 | |
| 座長: | 伊藤 正明(三重大学大学院医学系研究科 循環器・腎臓内科学) |
| 講演: | 中西 宣文(国立循環器病センター) |
| 「心Fabry病」 | |
| 座長: | 土居 義典(高知大学医学部 老年病・循環器・神経内科学) |
| 講演: | 中尾 正一郎(県民健康プラザ鹿屋医療センター 院長) |
| 「理学療法からみた循環器リハビリテーション」 | |
| 座長: | 片寄 正樹(札幌医科大学保健医療学部 臨床理学療法学講座) |
| 講演: | 村岡 卓哉(北海道文教大学人間科学部理学療法学科 教授) |
サンデーセッション
※タイトルをクリックすると詳細がご覧いただけます。
1) JCC-ACCジョイントシンポジウム [2009年9月20日(日)午前]
2) JCC教育プログラム [2009年9月20日(日)午後]
事務局:日本心臓病学会 教育担当
〒113-0033 東京都文京区本郷4-9-22 本郷フジビル
TEL:03-5802-0112 FAX:03-5802-0118 E-mail:edu@jcc.gr.jp
コメディカルセッション
| 超音波検査技師セッション「循環器領域におけるソノグラファーの貢献とその問題点」 |
| 看護師・保健師セッション「循環器診療における代替療法」 |
| 放射線技師セッション「X線CT、MR装置による心臓検査の現状」 |
| 薬剤師セッション「循環器医療への薬剤師の新たなる貢献」 |
第57回日本心臓病学会学術集会・日本心臓核医学会 ジョイントシンポジウム
| 「循環器関連疾患と自律神経障害」 | |
| 座長: | 西村 重敬(埼玉医科大学国際医療センター 心臓内科) 石田 良雄(国立循環器病センター 中央診断部門 核医学検査部) |
| 演者: | 坂田 泰史(大阪大学 循環器内科学) |
| 演者: | 藤木 明(富山大学病院 第二内科診療部門 循環器内科) |
| 演者: | 久下 裕司(北海道大学 分子イメージング講座) |
| 演者: | 外山 卓二(群馬県立心臓血管センター 循環器内科) |
日本心臓病学会・日本心臓血管外科学会ジョイントシンポジウム
| 「エビデンスに基づいたPCI,CABGの適応」 | |
| 座長: | 小川久雄(熊本大学)/ 坂田隆造(京都大学) |
| 演者: | 山岸正和(金沢大学)/一色高明(帝京大学) 髙本眞一(社会福祉法人 三井記念病院)/北村惣一郎(国立循環器病センター) |